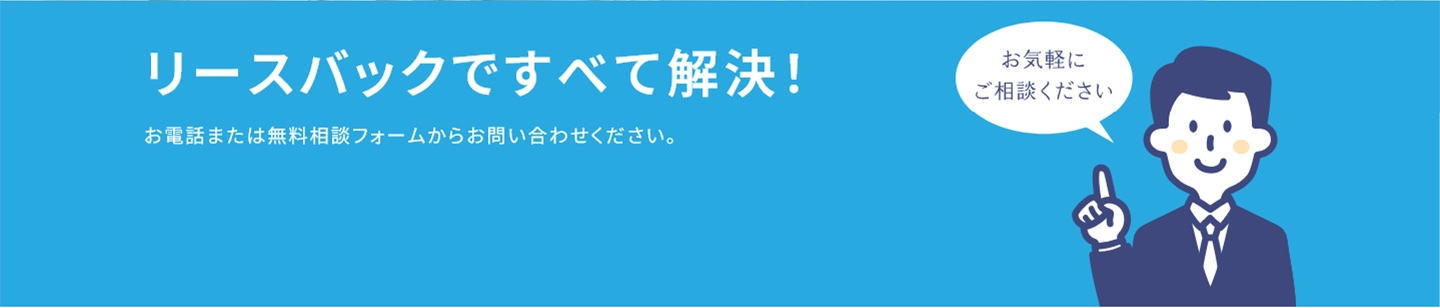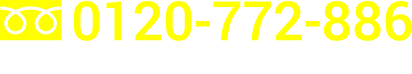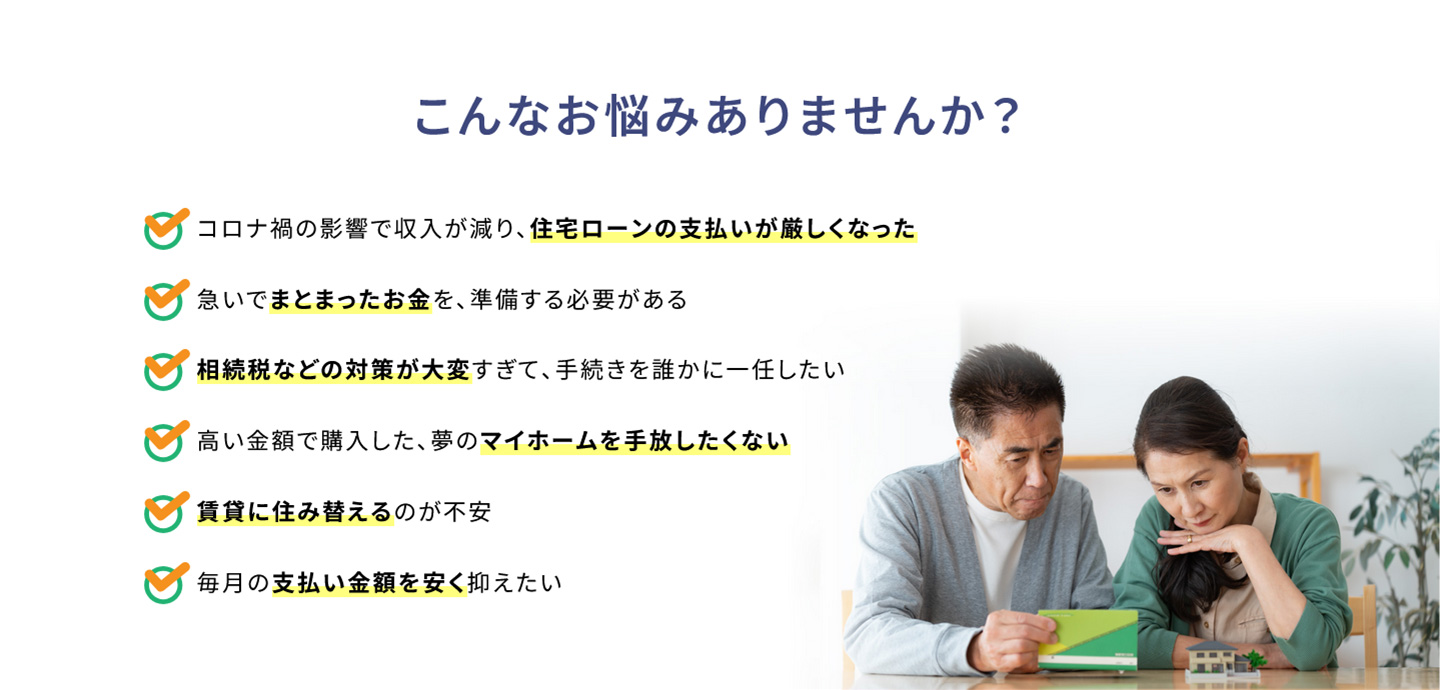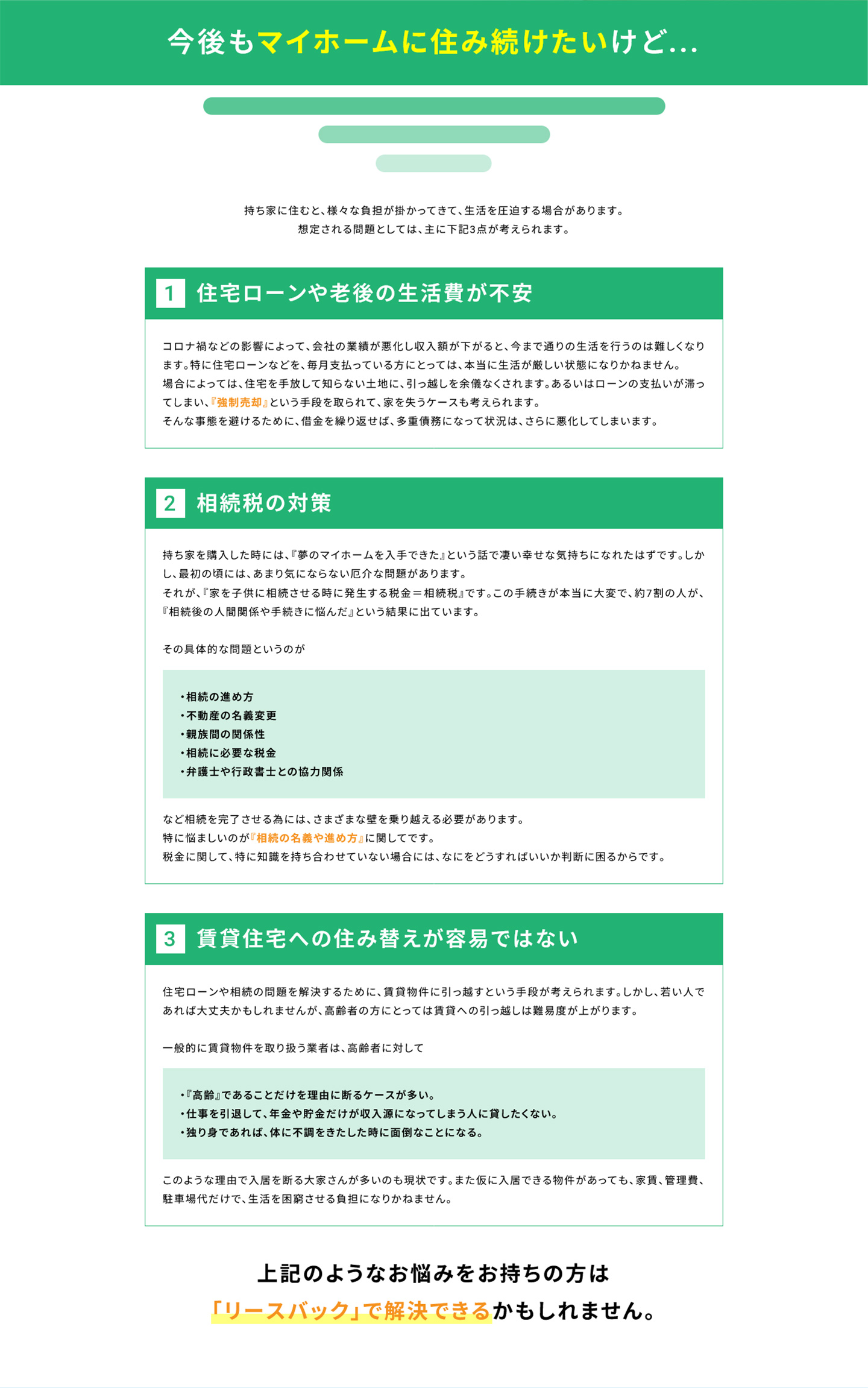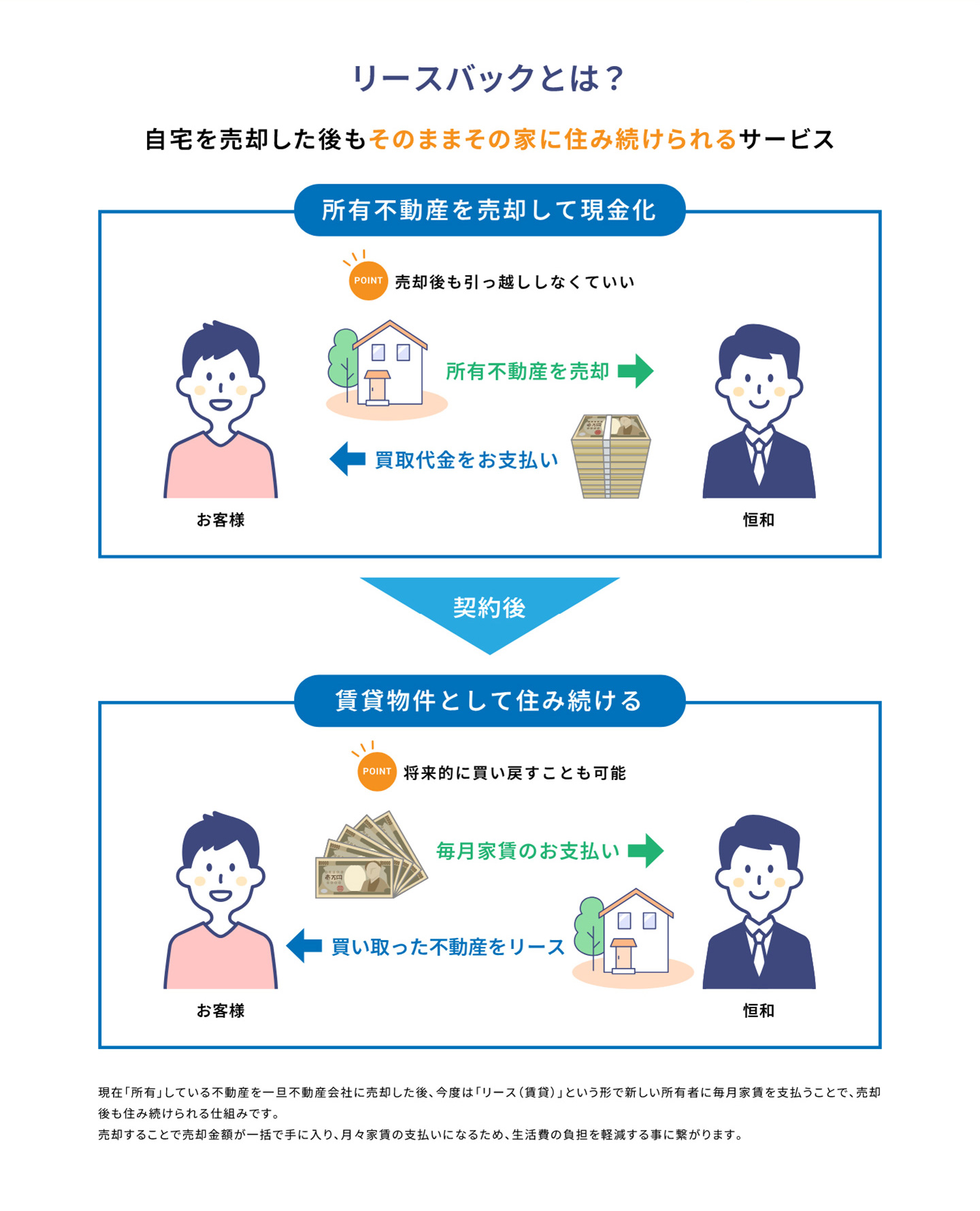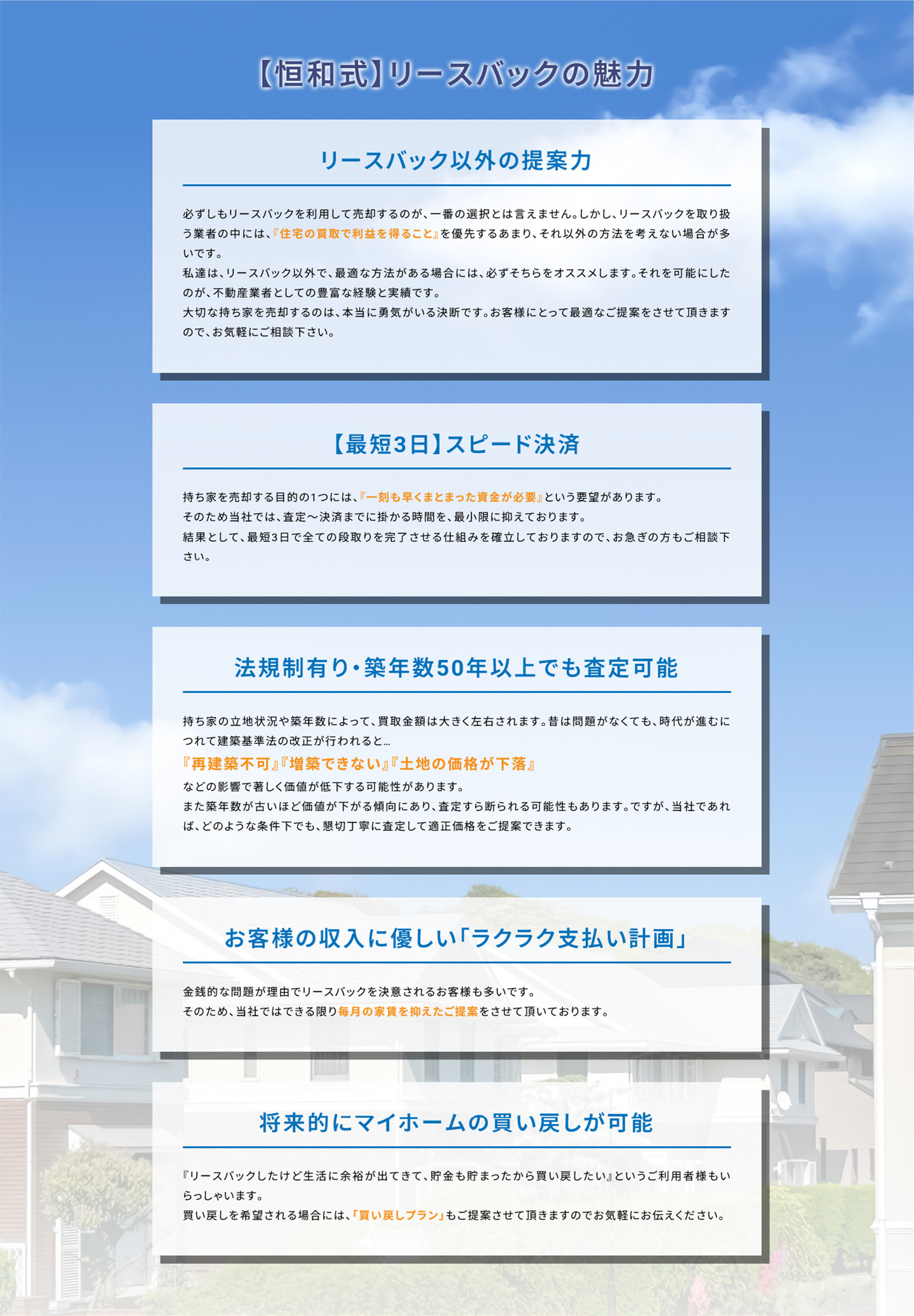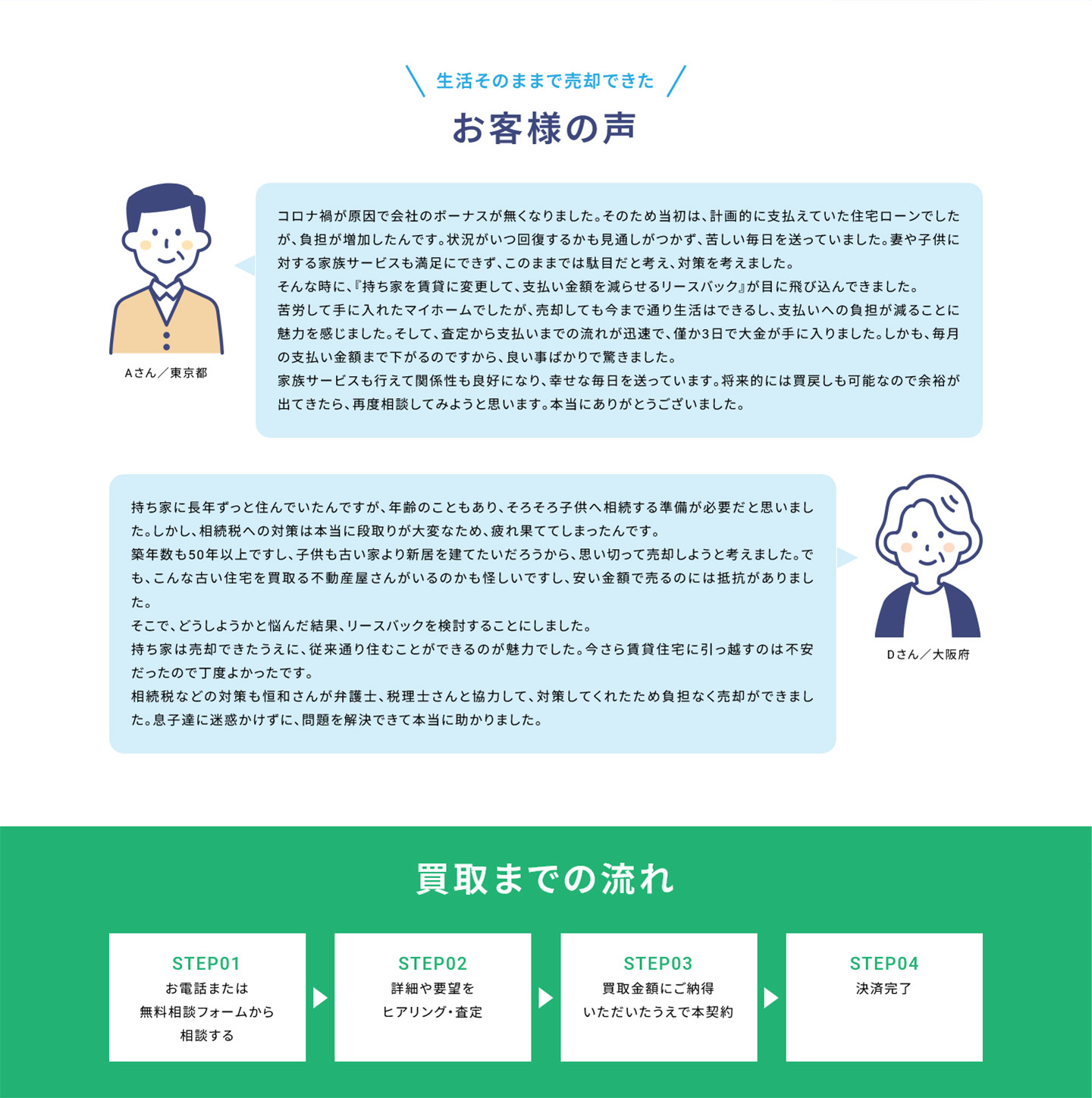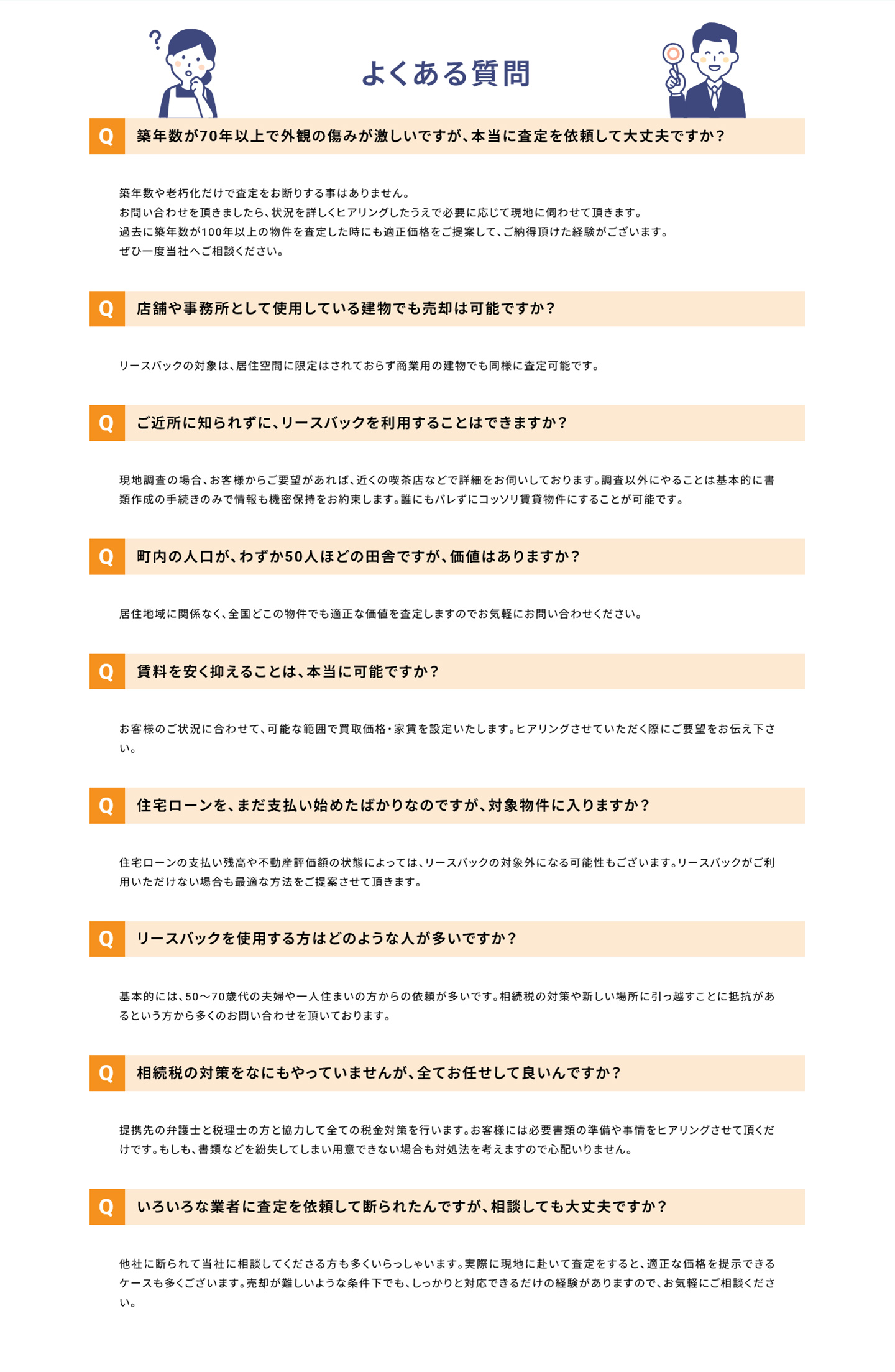本州と九州の架け橋である山口県でのリースバックに対応しております。 山口県は、関門橋と呼ばれる建設当時は最長となっていた道路橋があり、この橋のおかげで、車で九州と往来できるようになり、県内だけでなく、国内全体の発展にも繋がっています。 さらに山口県には橋だけでなく、世界初の海底トンネルとなる、関門鉄道トンネルが開通しており、電車、新幹線、車をはじめ歩行もできる人道も整備されており、まさに九州と本州を繋ぐ架け橋となっています。 そんな山口県は、3方を海に囲まれていることもあり、水産業が盛んです。 県を代表するあまだいは、水揚量日本一であり、はえ縄漁という釣針を多数つけた縄とその縄を支える長い縄で構成された縄を一定の深さで留めて捕まえる古事記の時期からある昔からの漁獲方法で、1匹1匹丁寧に捕まえられています。 そのため、傷が少なく鮮度も良いため、少し甘味のある美味しさを味わえることから県外からも人気で、今では高級魚とされているほどに至っています。 そして県内最大の人口を誇る本州の最西端に位置する下関市では、ふぐの水揚量が日本一となっており、県を代表する味覚にもなっています。 そんなふぐは、1598年から1888年まで、その毒性から禁止されていました。 日本初の内閣総理大臣である伊藤博文が、下関市を訪れた際その味に惹かれ1888年に解禁されました。 当時、ふぐは禁制されていましたが、魚がちょうど上手く獲れなかったため、代わりに下関市では一般料理と化していたふぐを出したとされています。 このような歴史があるふぐだけでなく、あんこうの水揚量も1位で、ほとんど捨てるところがないことから、あんこうの7つ道具とも呼ばれています。 さらに下関市は、近代捕鯨の発祥地ともされており、くじらが有名な地域でもあります。 捕鯨の文化自体は古く縄文時代から行われていたとされており、平安時代初期になると世界でも捕鯨文化が広がり、より効率の良い方法を模索しながら捕鯨文化は発展していきました。 昭和の時代には、戦後で食糧難だったこともあり、安価なくじら肉が重宝され給食メニューに出るほど全国でも普及していました。 ただ、捕鯨文化が各国で発展したことで、くじらの絶対数が減少したこともあり国際捕鯨委員会(IWC)の条約に基づき、商業的捕鯨が実質禁止になったことで、身近な食材ではなくなってしまいました。 そのため、下関でも商業捕鯨が行えなくなり、調査目的のみの捕鯨となりましたが、令和になり日本がIWCから脱退したことで、商業捕鯨が再開されたことで、くじら食が再興しつつあります。 リースバックの詳しいご相談は、リースバックに特化した不動産業者『株式会社恒和』にお任せください。 【対応エリア】 下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
 株式会社 恒和
株式会社 恒和