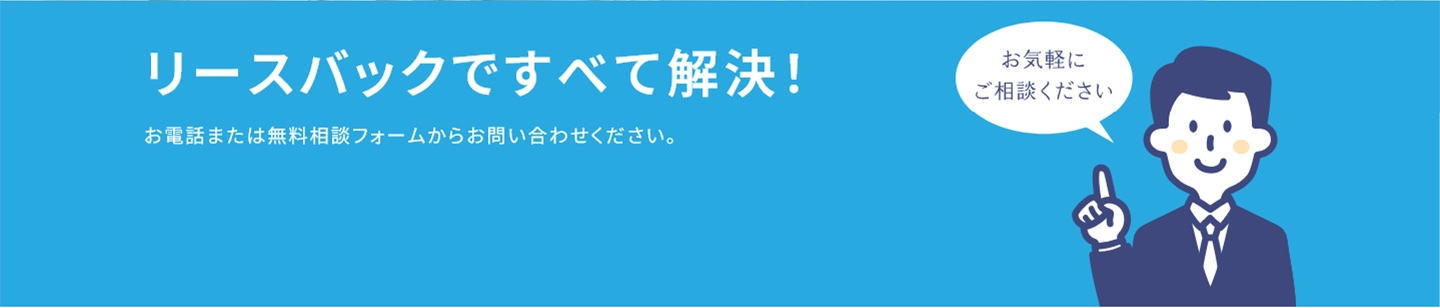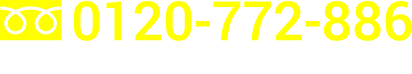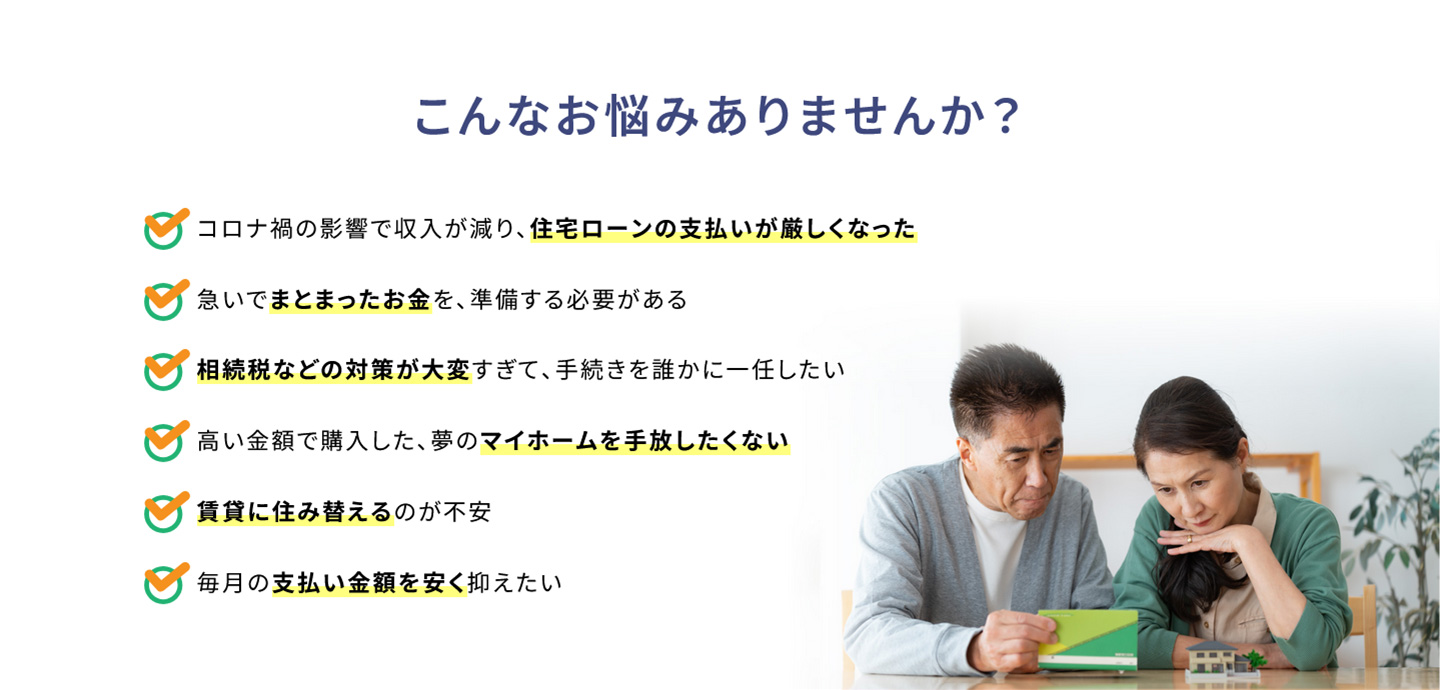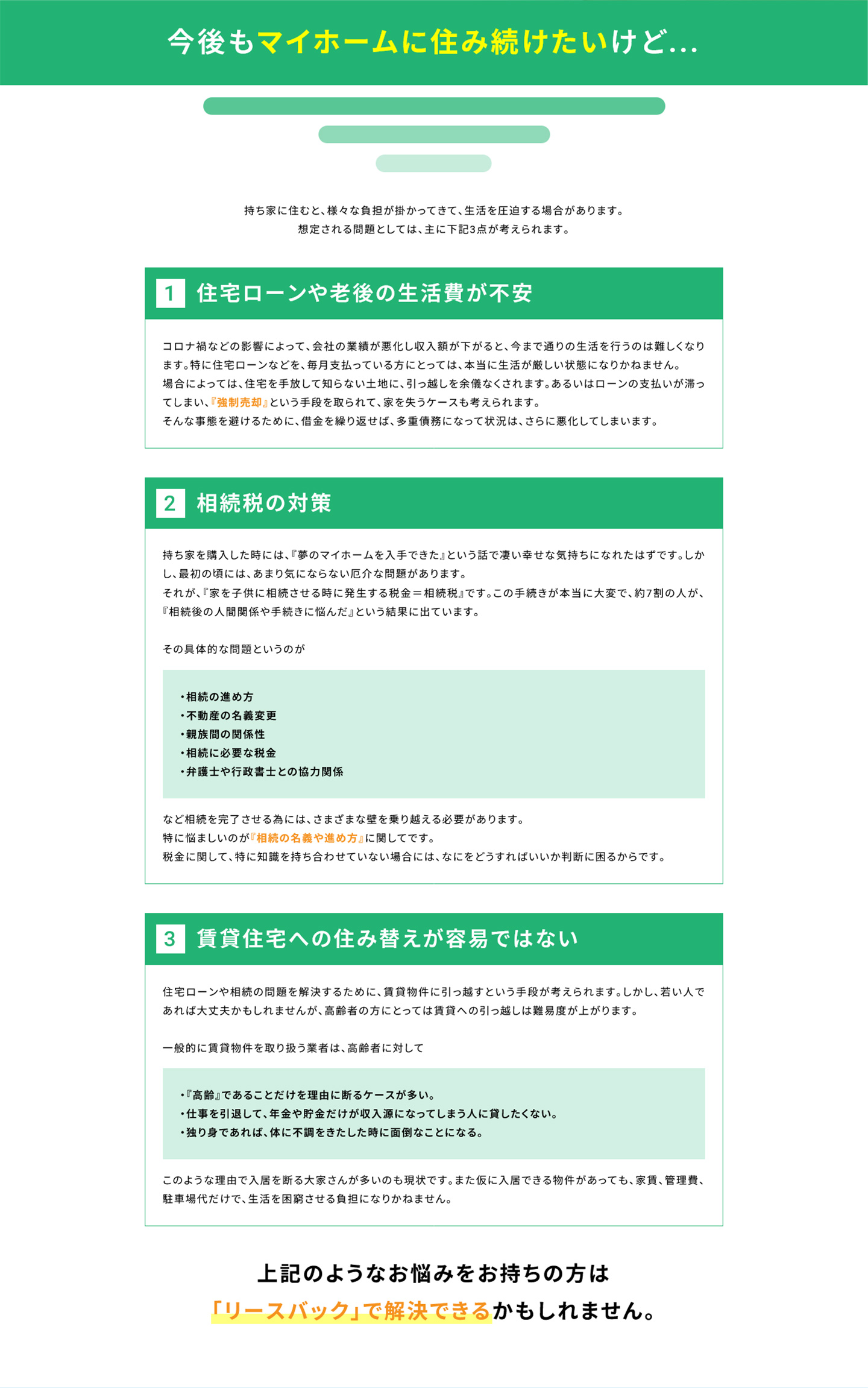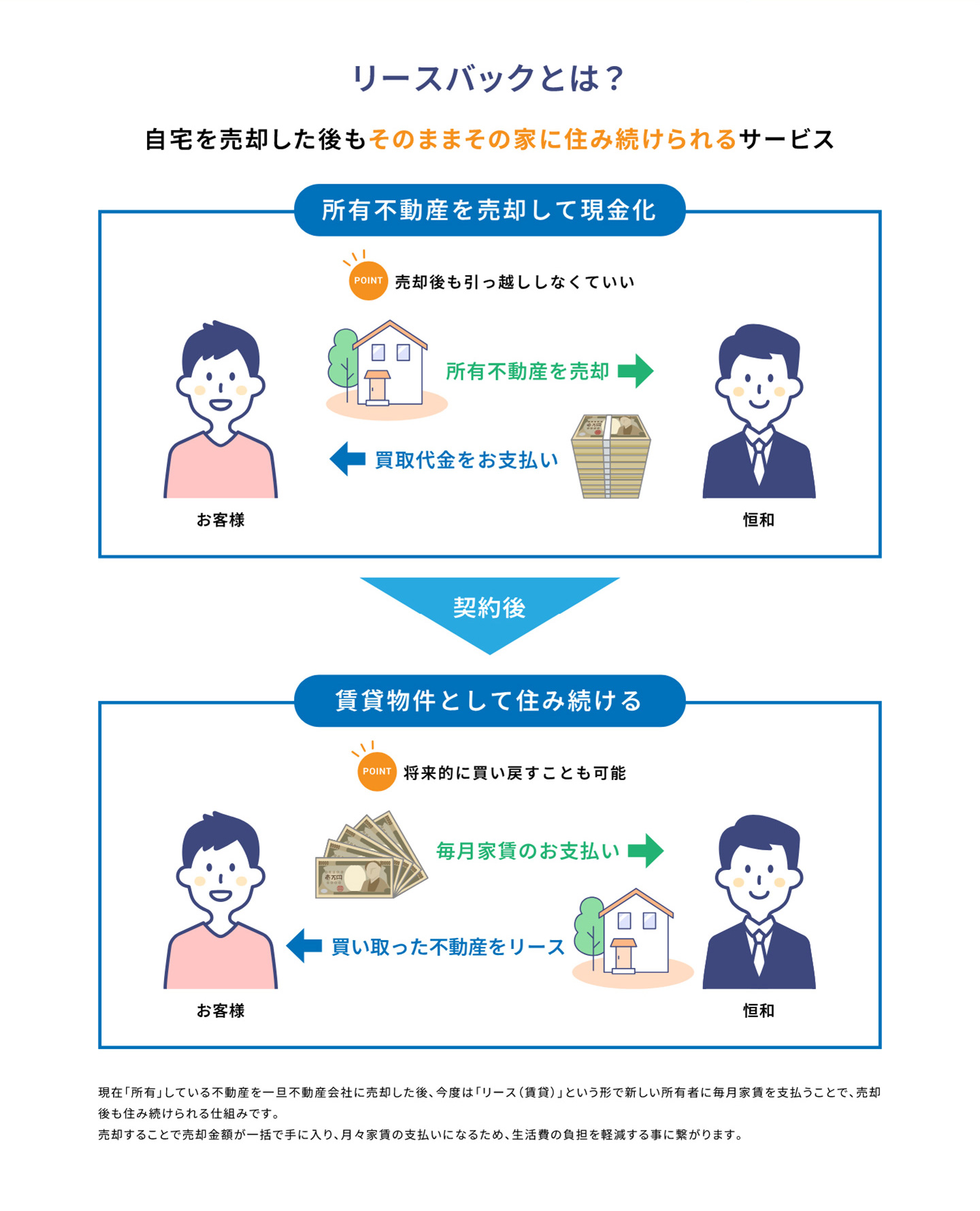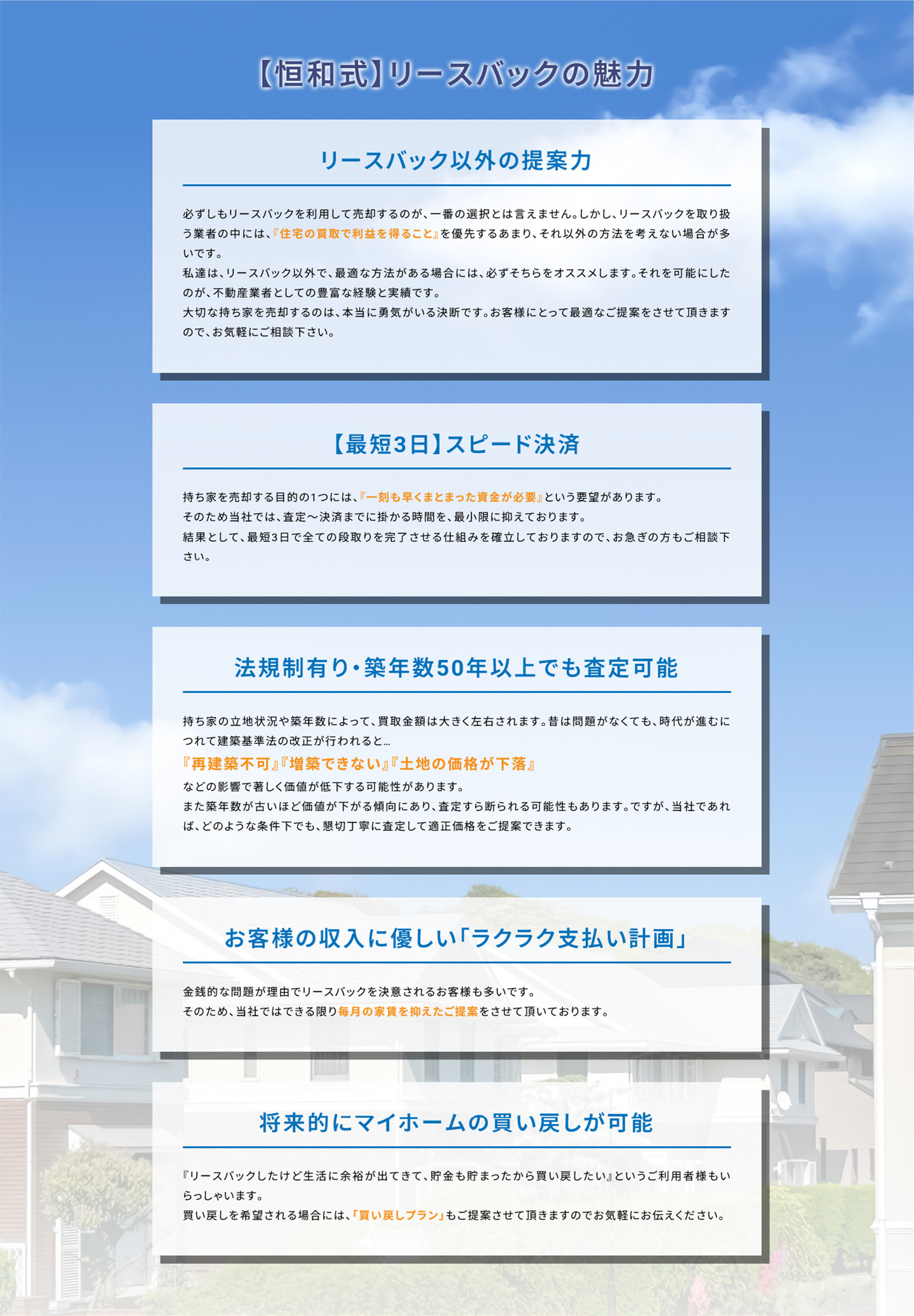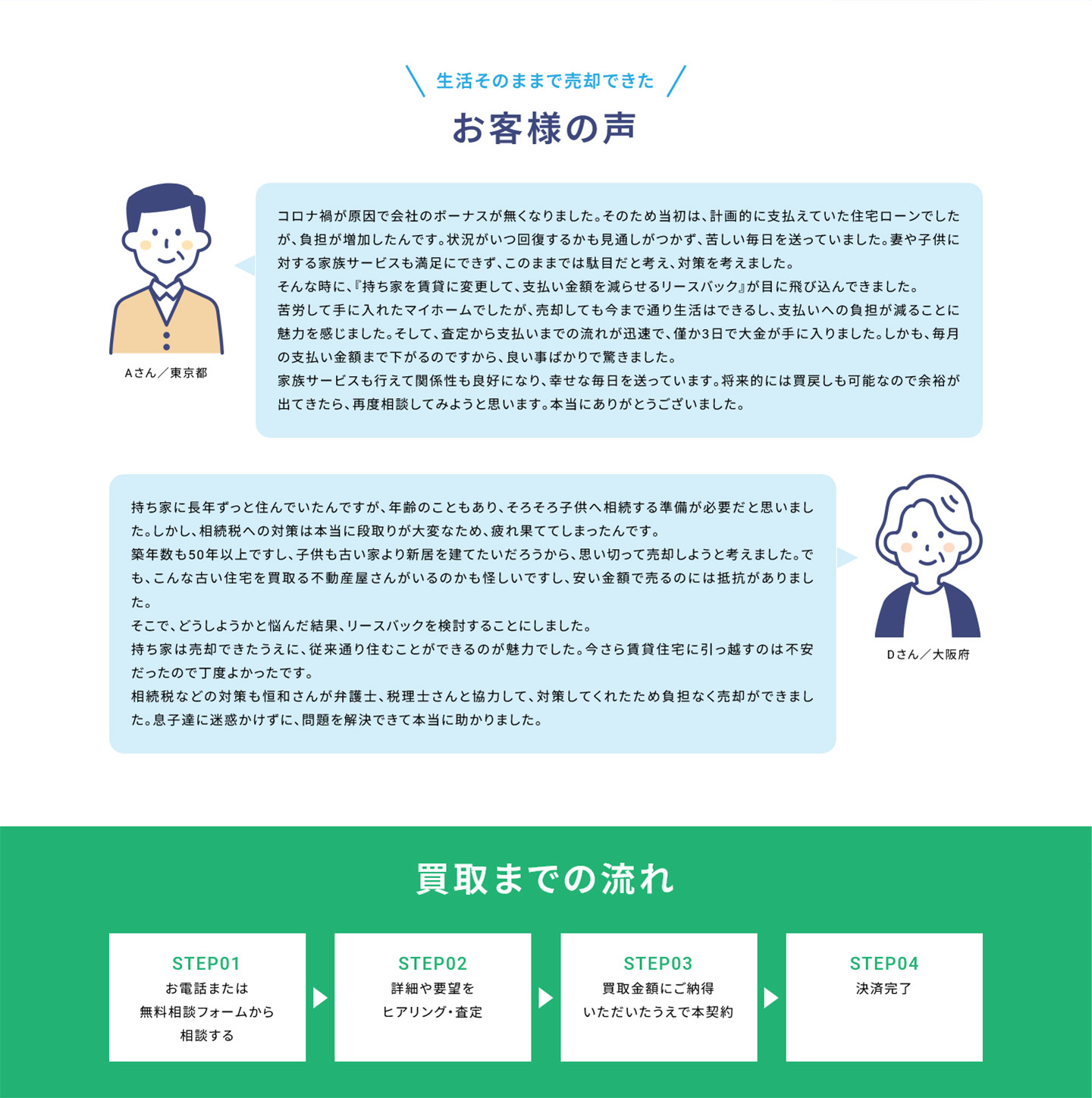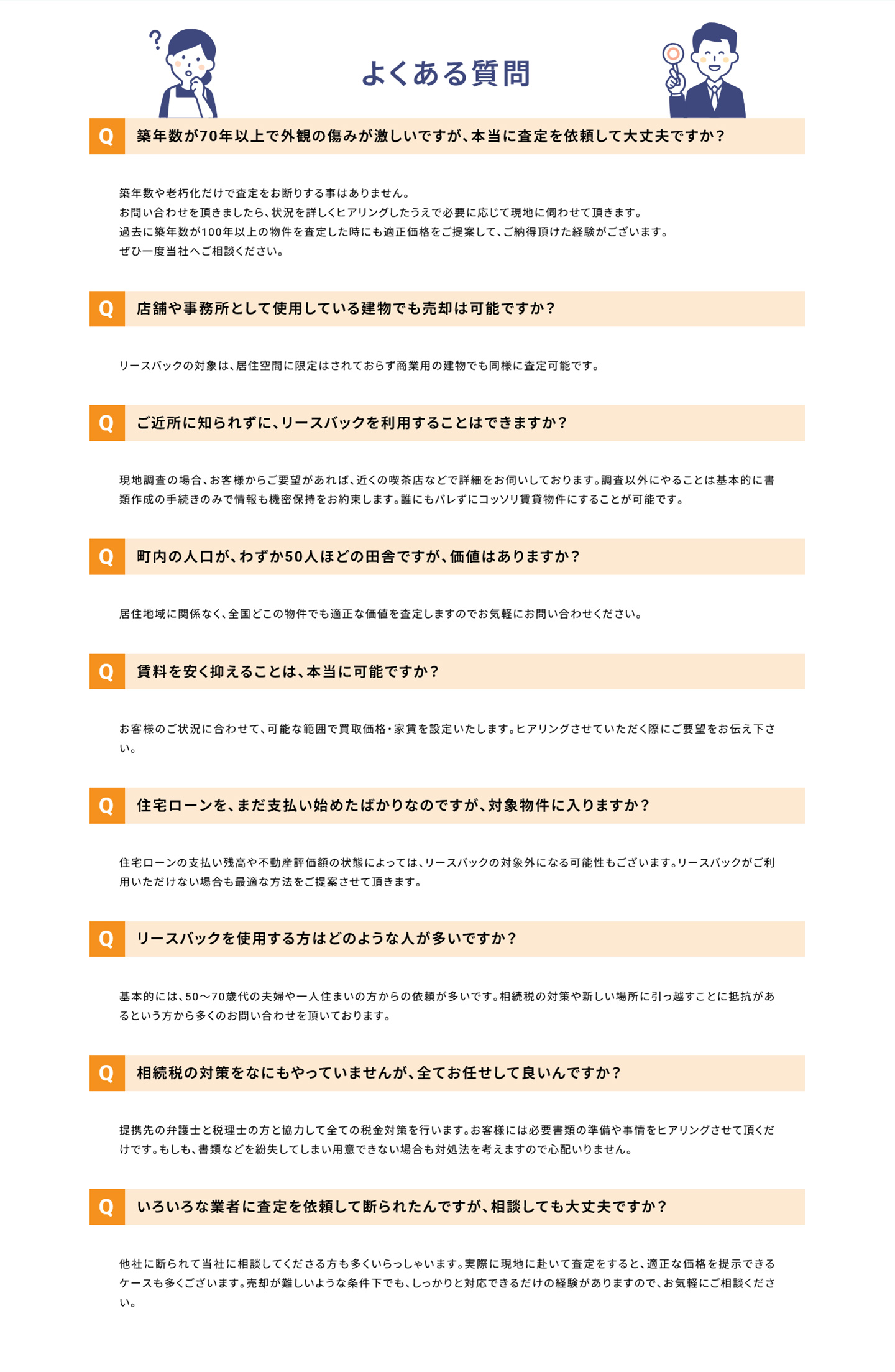九州の中でも水産業が盛んな地域として有名な佐賀県でのリースバックに対応しています。 古くはクジラ漁が盛んでしたが、商業捕鯨の禁止に伴い県内での捕鯨はなくなってしまいました。 ただ、捕鯨によって8代まで続く富を築いたとされる中尾家の屋敷が歴史建築物として残されており、県の重要文化財にもなっています。 現在は、捕鯨に変わり、イカが有名になっています。 一本釣りで丁寧に釣りあげられるイカを職人の早技よって透明なまま食べる活造りが有名で県の名物になっています。 養殖も盛んに行われており、マダイをはじめとする魚だけでなく、真珠(アコヤガイ)、アワビといった貝類の養殖が目玉になっています。 そして県内屈指の水産物が、海苔であり国内総生産1位となっています。 支柱養殖と呼ばれる満潮の際に海水の栄養分を得て、干潮時の日光で、アミノ酸を増やしうまみ成分を与える製造方法を行っており、これは、日本一の干満差を誇る有明海だからこそより良い海苔ができあがり、有明海苔として県のブランドにもなっています。 また、佐賀県はかつて豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った際の拠点とされたエリアでもあります。 その時に連れてこられた朝鮮陶工の方々によって、陶器技術が広まっていき、きめ細やかさと透明感溢れる白磁に塗られた藍色の顔料で描いた赤絵が特徴の有田焼は、今では佐賀県を代表するブランドになりました。 さらに鎖国化の日本でも当時貿易が可能であった中国がカンボジアへオランダがハノイに輸出したことをきっかけに、世界に広がり始め、当時の有田焼が残っている地域もあるほど人気の磁器です。 その美しさと歴史的価値から高額で取引されているものもあり、特に骨董品と呼ばれるのが有田焼の中でも『古伊万里様式』と呼ばれる江戸時代に生産されたもので、濃い藍色を贅沢に使い赤や金でまぶされた磁器です。 有田焼の代表的な様式として、濁手(にごしで)と呼ばれる乳白色の素地を用いて、色とりどりの彩色を施しつつ、乳白色を輝かせる『柿右衛門様式』、各地の将軍や大名への贈り物として当時佐賀県を統治していた鍋島藩によって作られた『鍋島藩窯様式』といった様式が有名です。 現在では、日用的に使えるよう安価な有田焼も多数存在しており、手に取りやすくなっています。 有田焼以外にも粘土を原料として作られ使うほどに味わいが出てくる魅力がある『唐津焼き』、熱したガラスを吹いて形作る宙吹き製法と呼ばれる方法で作られた『肥前びーどろ』といった工芸品は、佐賀県を代表する工芸品となっています。 リースバックの詳しいご相談は、リースバックに特化した不動産業者『株式会社恒和』にお任せください。 【対応エリア】 佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町
 株式会社 恒和
株式会社 恒和